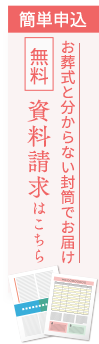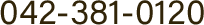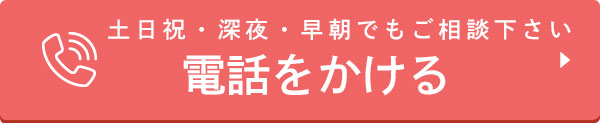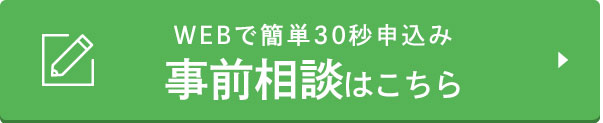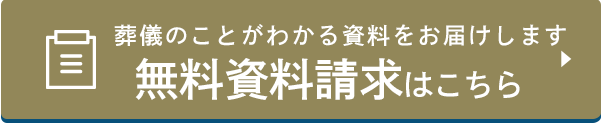葬儀の基礎知識一覧
法事のお返しとは

「香典返し」と「法事のお返し」
法事のお返しと香典返しの違い
ご葬儀や法要の場では、「香典返し」と「法事のお返し」という言葉を耳にします。
どちらもお礼の気持ちを伝えるものですが、贈る時期や目的が異なります。
香典返しとは
葬儀や告別式の際にいただいた「香典」へのお礼としてお渡しする品のことです。
*当日返し 葬儀・告別式の当日に、会葬御礼の品として返礼品(タオル・お茶・お菓子など)を渡します。金額に目安は 「いただいた香典の半額程度」ではなく「一律3,000円前後」にすることが多いです。
*後返し 四十九日(忌明け)を過ぎた頃に、いただいた香典額の「半分程度(半返し)」を目安にお返しします。後返しには「故人の冥福を祈り、無事に忌明けを迎えたことのご報告」「生前中のご厚情への感謝」という意味が込められています。まとめて送る場合は、香典帳の整理をしてから個別に金額を調整するとよいでしょう。

法事のお返しとは
一方、「法事のお返し」は、年忌法要(1周忌・3回忌など)にご参列くださった方へのお礼としてお渡しするものです。
こちらも「ご供養にお越しいただいたお礼」として、会食後やお帰りの際に直接お渡しするのが一般的です。
金額の目安は、お供えやお布施などをいただいた場合は、その半分程度
特に何もいただかずに参列だけの方には、1,000~3,000円程度の品が多く選ばれています。
法事はお祝い事ではないため、華美にならない落ち着いた品を選びます。
「消えもの(お茶・お菓子・石けんなど)」が無難で人気です。
参列者には、会食後やお帰りの際に直接お渡しします。
法事のお返し・香典返しの掛け紙(のし)マナー
お返しの品には、感謝の気持ちを表す「掛け紙(のし紙)」を掛けるのが一般的です。
ただし、お祝い事とは異なり、弔事専用の掛け紙と表書きの使い分けがあります。
のし紙の種類
弔事では、「のし(熨斗)」の付いたお祝い用の掛け紙は使用しません。
代わりに、「結び切り」または「黒白(または銀白)」の水引が印刷されたものを使います。
「のし」は慶事用のため、弔事ではのしの無い掛け紙を使うのが正解です。
地域によっては関西などで黄白の水引を使う場合もあります。
表書き(上書き)の書き方
お返しの目的によって表書きが変わります。
葬儀・忌明け(香典返し)→ 志(こころざし)
法事(年忌法要)のお返し→ 志・粗供養・偲び草 など
「志」は全国共通で使える万能表記です。
関西圏では「満中陰志」や「粗供養」を使うことが多いです。
「偲び草(しのびぐさ)」も上品で柔らかな印象を与えます。
名前(下書き)の書き方
故人の姓(例:山田)または喪主の名前(山田 太郎)
*故人の名前ではなく喪主またはご遺族の名義で出すのが基本です。
*四十九日までは「喪中」扱いのため、表書きは薄墨で書くこともあります。
掛け方のマナー(内のし・外のし)
*内のし「品物に直接のし紙を掛け、その上から包装」郵送や宅配で送る場合に多いため
*外のし「包装紙の上からのし紙を掛ける」手渡しの際に感謝の気持ちを強調できるため
主な年忌法要と時期の目安
一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・・・・
「三回忌」は亡くなった年を1回目と数えるため、実際には2年後に行います。
命日が平日などの場合は、命日の前の週末に繰り上げて営むのが一般的です。
三十三回忌をもって「弔い上げ」とし、それ以降の法要を省略する地域が多いです。
法要を営む理由
年忌法要は、故人の冥福を祈るだけでなく、遺族や親族が集まり、絆を確かめ合う大切な行事です。
そのため、近年は「一周忌」「三回忌」「七回忌」「十三回忌」など、節目を中心に行うケースが増えています。
宗教・形式別の法要(追悼行事)の時期と意味
仏教の「年忌法要」にあたる行事は、宗教ごとに名称や時期が異なります。
ここでは代表的な「無宗教」「キリスト教」「神道」の場合をまとめました。
無宗教の場合
無宗教葬を行った場合、特定の宗教儀礼は行わず、【自由な形で故人を偲ぶ会(メモリアル)】を開くことが多いです。
お別れの会・偲ぶ会 → 四十九日頃、または命日や節目「会食や献花など、形式にとらわれないスタイル」
一周忌・三回忌相当の追悼会 → 1年後・2年後「仏教の年忌に合わせて行うことも多い」
命日供養・メモリアルデー → 毎年の命日や誕生日など「家族や親しい方だけで行うケースが多い」
*宗教儀礼がない分、命日や故人の誕生日、亡くなった季節などを節目に設定します。
花や音楽、思い出の映像などを取り入れ、「感謝と追悼の会」として行うのが主流です。
キリスト教の場合(カトリック・プロテスタント)
キリスト教では「法要」という言葉は使わず、「追悼ミサ」や「記念礼拝」という形で行います。
カトリックの場合
追悼ミサ → 30日後(1か月後)「30日祭(サーティー・デイズ・ミサ)とも呼ばれる」
年忌・記念ミサ → 1年後(命日近く)「一周忌相当。以後、2年目・3年目などにも行う場合あり」
プロテスタントの場合
記念礼拝 → 1か月後・1年後など「家族・教会で行う追悼の礼拝」
メモリアル礼拝 → 毎年命日や召天記念日に「故人を思い出し、感謝を捧げる時間」
カトリックでは「追悼ミサ」、プロテスタントでは「記念礼拝」という形で行います。
日取りは命日にこだわらず、日曜日や集まりやすい日に行うのが一般的です。
神道の場合
神道では「法要」ではなく、「霊祭(れいさい)」や「式年祭(しきねんさい)」と呼ばれます。
仏教の法要に近い意味を持ち、故人の御霊を慰め、祖霊として祀る儀式です。
十日祭 → 亡くなって10日目
二十日祭 → 亡くなって20日目
三十日祭 → 亡くなって30日目
五十日祭 → 亡くなって50日目「四十九日法要に近い、忌明けの祭り」
百日祭 → 百か日法要に相当
一年祭 → 一周忌に相当
三年祭 → 三回忌に相当
五年祭・十年祭・二十年祭・五十年祭
*神道では「忌明け」が五十日祭にあたります。
以後は一年祭・三年祭・五年祭・十年祭などを営み、五十年祭を「合祀祭(ごうしさい)」として、祖霊舎に合祀します。
※ご葬儀後の香典返しやご法要後の引き出物など、各種返礼品のご相談を承っております。
故人を偲ぶお気持ちを大切に、心を込めたご提案をさせていただきます。
東京フラワーセレモニー