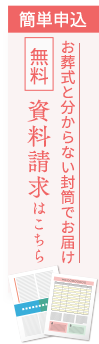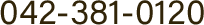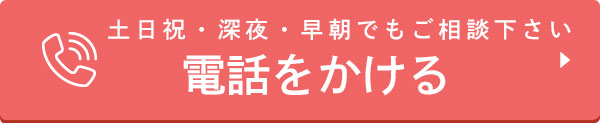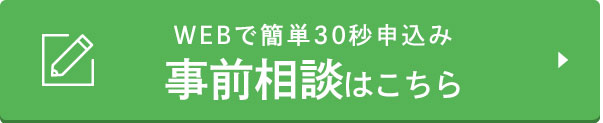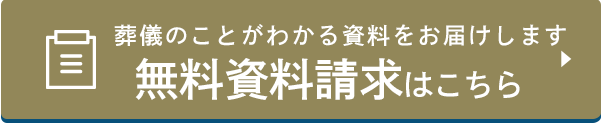葬儀の基礎知識一覧
弔問する時の服装・故人との対面・お悔やみとは?
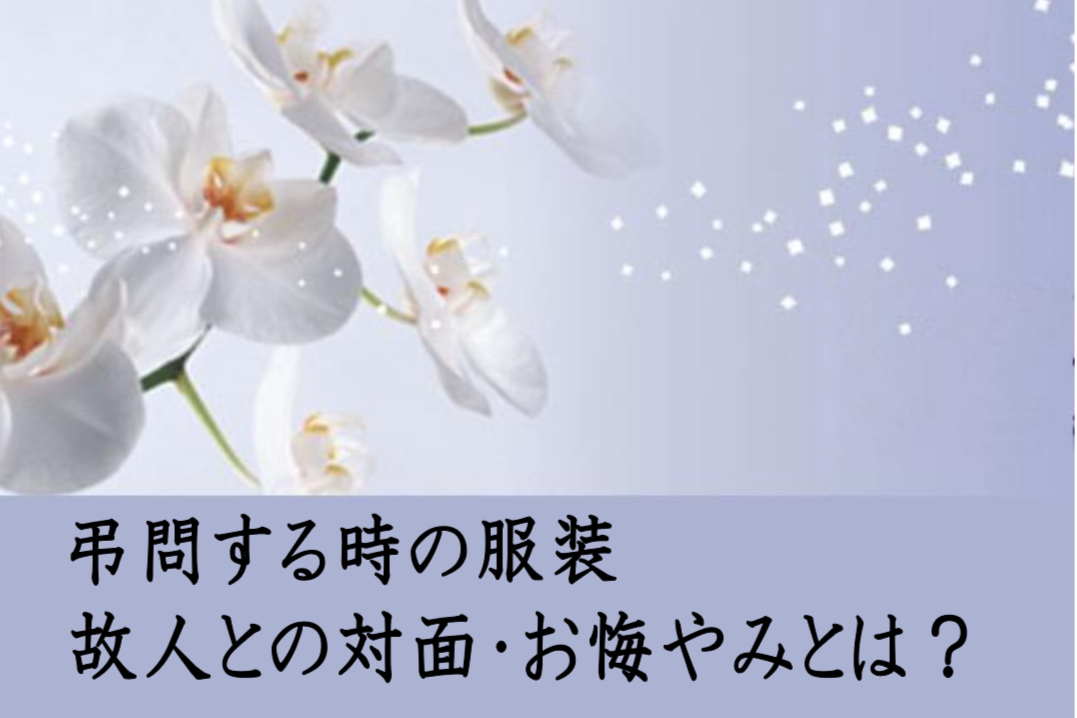
弔問時の服装・故人との対面・お悔やみとは?の基本マナーを
~小金井市の葬儀社 東京フラワーセレモニーがご紹介~
弔問するときの服装は — 失礼のない身だしなみを心がけましょう
弔問とは? — 意味とタイミングを確認
「弔問(ちょうもん)」とは、亡くなられた方のご遺族を訪ね、お悔やみの気持ちを伝えることを指します。
葬儀・告別式に参列できない場合や、後日あらためてお悔やみに伺うことを言います。。
弔問の際には、悲しみに寄り添う気持ちを服装や態度で表すことが大切です。
華美な装いを避け、控えめで清潔感のある服装を心がけましょう。
※弔問の服装は、訪問するタイミング(通夜前・葬儀後・後日の弔問)によって異なります。
通夜や葬儀前に弔問する場合
通夜や葬儀の前に弔問する場合は、喪服を着用せず、地味な平服で構いません。
まだ葬儀の日程が決まっていない場合は、喪服で訪ねると「死を待っていた」印象を与えてしまうことがあります。
男性:
ダークスーツ(黒・紺・濃いグレー)
白のワイシャツ
地味なネクタイ(黒またはグレー)
女性:
黒・紺・グレーのワンピースまたはスーツ
アクセサリーは控えめに(真珠のみ可)
ストッキングは黒または肌色、靴は黒のシンプルなパンプス
通夜・葬儀に参列する場合
通夜や葬儀・告別式に参列する際は、「正式な喪服(ブラックフォーマル)」を着用します。
男性:
黒の礼服(シングルまたはダブルスーツ)
黒のネクタイ・靴下・靴(光沢のない革靴)
女性:
黒のワンピース・アンサンブル・スーツ
黒のストッキング・靴(ヒールは3cm程度まで)
アクセサリーは白または黒の真珠のみ
香水や派手なネイル・髪飾りは控えましょう。
喪に服す姿勢を服装で表すことが大切です。
葬儀後(後日の弔問)の場合
葬儀後、日を改めてご遺族宅を訪問する場合は、「略式の服装(地味な平服)」で構いません。
黒やグレーなど落ち着いた色合いの服装を選び、清潔感を意識しましょう。
男性・女性ともに「控えめ・清楚」を意識することで、遺族への敬意が伝わります。
弔問時の持ち物・身だしなみチェック
弔問の際は、服装だけでなく身だしなみや持ち物にも注意が必要です。
数珠(通夜・葬儀参列時は必携)
香典(新札は避け、袱紗に包む)
靴は黒で光沢のないもの
派手なアクセサリー・香水は控える
弔問時のマナーは「故人とご遺族に敬意を示す」ことが目的です。
形式よりも、丁寧な言葉づかいと落ち着いた態度が何より大切です。
控えめな装いが最大のマナー
弔問するときの服装は、故人とご遺族への敬意を示す大切なマナーです。
華やかな服装を避け、落ち着いた色合いと清潔感を意識しましょう。
当社では、通夜・葬儀だけでなく、弔問や法要に関するマナー・作法についても丁寧にご案内しております。
ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
故人との対面 — 最後のお別れの時間を大切に
故人との対面とは
「故人との対面」とは、ご逝去後に故人さまと、お会いする時間のことです。
ご家族や親しい方が故人のお顔を見てお別れを告げる、大切で尊いひとときです。
病院や施設で亡くなられた場合は、医師による死亡確認のあと、ご遺族が病室などで故人と対面するのが一般的です。
葬儀社が到着後は、ご希望の安置場所(自宅・斎場など)へ故人をお送りし、安置後にも改めて対面の時間を設けます。
※安置後の対面につきましては、メイク後の対面をお勧めしています。
https://www.tf-ceremony.jp/area/koganei/koganei-knowledge/2080/
病院での対面の流れ
医師による死亡確認
ご逝去が確認されると、医師から説明を受け、「死亡診断書」が発行されます。
*ご遺族による対面
病室や専用の対面室に案内され、故人さまと最後のご挨拶をします。
このときは涙をこらえず、自然にお別れの言葉をかけてかまいません。
*葬儀社への連絡と搬送準備
故人との対面が済んだら、葬儀社へ搬送の依頼を行います。
24時間いつでも対応できる葬儀社に連絡し、安置先をご相談ください。
※「まだ何も決まっていない」「どこに安置すればいいかわからない」場合も、どうぞご安心ください。
東京フラワーセレモニーが丁寧にご案内いたします。
ご自宅・安置所での対面
弊社スタッフによって故人を搬送した後は、ご自宅または安置施設で改めて対面します。
このとき、弊社のスタッフが清拭(せいしき)やお着替えなどの処置を行い、穏やかなお姿でお迎えできるよう整えます。
ご遺族・ご親族は順番にお顔を見ながら、お別れの言葉をかけます。
「今までありがとう」「お疲れさまでした」など、感謝の気持ちを伝える時間として大切にお過ごしください。
※小さなお子さまやご高齢の方も、無理のない範囲で対面に立ち会うことができます。
対面時のマナーと心構え
故人との対面に特別な作法はありませんが、以下の点を意識すると、より穏やかにお別れができます。
・落ち着いた服装で(派手な色や香水は控える)
・故人のご遺体や遺品に触れる場合は、葬儀社やご家族の指示に従う
・写真撮影は控える(記録よりも心の中に残す)
・静かに、心を込めてお別れをする
対面は「悲しみを受け入れる第一歩」とも言われています。
時間を気にせず、ゆっくりと故人との最後の時間をお過ごしください。
※故人との対面は「ありがとう」を伝える時間
故人との対面は、人生の節目としてとても大切な儀式です。
悲しみの中でも、これまでの思い出や感謝の気持ちを胸に、穏やかにお別れを告げましょう。
当社では、搬送・安置・納棺などの際に、ご遺族が安心して対面できるよう丁寧にサポートしております。
初めての方にも分かりやすくご案内いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
24時間365日対応・ご相談無料
故人との対面や安置についてのご質問・ご不安など、いつでもお電話ください。
お悔やみとは — 故人とご遺族に寄り添う心の言葉
お悔やみの意味
「お悔やみ(おくやみ)」とは、人の死を悲しみ、そのご遺族に対して哀悼の意を表すことを意味します。
言葉で表すときは「お悔やみ申し上げます」「ご愁傷様でございます」などの表現を使います。
お悔やみの言葉には、「悲しみを分かち合い、相手の心に寄り添う」という気持ちが込められています。
形式よりも、心を込めて伝える姿勢が何よりも大切です。
お悔やみを伝えるタイミング
お悔やみは、訃報を知ったとき・通夜や葬儀に参列したとき・後日に弔問したときなど、さまざまな場面で伝えます。
通夜・葬儀の場で伝える場合
弔問時に、ご遺族へ一言だけ静かに伝えるのが基本です。
例:「このたびはご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」
長い言葉や理由づけは避け、短く丁寧に気持ちを伝えましょう。
電話・手紙・メールで伝える場合
直接伺えない場合は、「お悔やみの手紙(弔電・弔文)」やメールなどで伝えることもあります。
形式的な文面でも、故人への思い出やご遺族をいたわる気持ちを添えると良い印象です。
お悔やみの言葉の例
お悔やみの言葉は、状況や関係性によって使い分けることができます。
・ 一般的な言葉
「心よりお悔やみ申し上げます」
「ご冥福をお祈りいたします」
「ご愁傷様でございます」
・親しい関係の方へ
「突然のことで言葉もございません」
「〇〇さんの優しい笑顔が忘れられません」
「どうかお力を落とされませんように」
・ビジネス関係の場合
「ご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます」
「ご遺族の皆様に心より哀悼の意を表します」
※「ご苦労様」「頑張って」などの表現は、遺族の悲しみに配慮して避けましょう。
お悔やみのマナー
お悔やみの言葉を伝える際には、言葉づかいだけでなく態度・服装・場の雰囲気にも気を配ることが大切です。
・服装は地味で落ち着いた色(通夜・葬儀では喪服)
・声は静かに、短く丁寧に
・相手の悲しみに共感する姿勢を大切に
・不用意に故人の死因などを尋ねない
・お悔やみの言葉は「相手を慰める」よりも「悲しみを共有する」ことを意識しましょう。
お悔やみとは「思いやりの表現」
お悔やみとは、形式的な挨拶ではなく、相手の悲しみに寄り添う心の表現です。
言葉は短くても、真心を込めて伝えることで、ご遺族に安心と支えを届けることができます。
お悔やみの言葉 例文集
~小金井市の葬儀社 東京フラワーセレモニーがご紹介~
一般的なお悔やみの言葉(基本の表現)
まずは、どんな場面でも使える一般的な言葉からご紹介します。
迷ったときは、短く、心を込めて伝えることが何より大切です。
例文:
「心よりお悔やみ申し上げます。」
「ご冥福をお祈り申し上げます。」
「このたびはご愁傷様でございます。」
「突然のことで、言葉もございません。」
「謹んで哀悼の意を表します。」
※長い言葉よりも、静かに、短く伝えるほうが丁寧で思いやりが伝わります。
通夜・葬儀で使うお悔やみの言葉
通夜や葬儀の場では、ご遺族が多くの方に対応しているため、一言で思いを伝えるのが礼儀です。
例文:
「ご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」
「大変な中、どうかお体をお大事になさってください。」
「突然のことで、お気持ちをお察しいたします。」
「在りし日のお姿が偲ばれます。どうぞ安らかにお眠りください。」
※あくまで「ご遺族を励ます言葉」ではなく、「悲しみを共有する言葉」を心がけましょう。
親しい友人・知人へのお悔やみの言葉
親しい関係の場合は、形式よりも心からの思いを込めた言葉がふさわしいです。
思い出を一言添えると、あたたかみが伝わります。
例文:
「突然の知らせに驚いております。〇〇さんの優しい笑顔が忘れられません。」
「在りし日の〇〇さんを思うと胸がいっぱいです。どうぞ安らかにお眠りください。」
「悲しい気持ちでいっぱいです。どうかご遺族の皆様もお力を落とされませんように。」
「お手伝いできることがあれば、いつでもお声がけください。」
※「頑張って」「元気を出して」といった励ましの言葉は、かえって負担になることがあります。
ビジネス関係の方へのお悔やみの言葉
取引先や上司・同僚など、ビジネス上の関係者に対しては、丁寧で控えめな言葉づかいが適しています。
例文:
「ご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。」
「ご遺族の皆様に謹んで哀悼の意を表します。」
「ご生前のご厚誼に深く感謝申し上げ、心よりご冥福をお祈りいたします。」
「ご逝去の報に接し、驚きと悲しみでいっぱいです。謹んでお悔やみ申し上げます。」
※ビジネス文書や弔電では、「ご冥福」「謹んで」「哀悼の意」などの正式表現が望まれます。
お悔やみの手紙・弔電で使える文例
お悔やみの手紙(弔文)や弔電を送る場合は、丁寧で落ち着いた文体を意識します。
・弔電・弔文の文例
このたびはご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
ご生前のご厚情に深く感謝申し上げ、安らかなご冥福をお祈りいたします。
・親しい方へのお悔やみの手紙
突然のことで言葉もございません。
〇〇さんにはいつも親しくしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
どうか安らかにお眠りください。
避けたい言葉・注意したい表現
お悔やみの場では、縁起を連想させる言葉や明るい表現は避けましょう。
・避けるべき言葉の例
「再び」「また会いましょう」(重ね言葉・不幸の繰り返しを連想)
「生きていたころは…」(生を直接的に表す表現)
「頑張って」「元気を出して」(遺族に負担をかける場合あり)
言葉よりも「心」が伝わるように
お悔やみの言葉に正解はありません。
大切なのは、相手の悲しみに寄り添う気持ちを込めて伝えることです。
言葉が少なくても、心を込めて静かに伝えれば、それが何よりの慰めとなります。
当社では、葬儀や弔問時のマナー・言葉づかいについても丁寧にご案内しております。
ご不安なことがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。